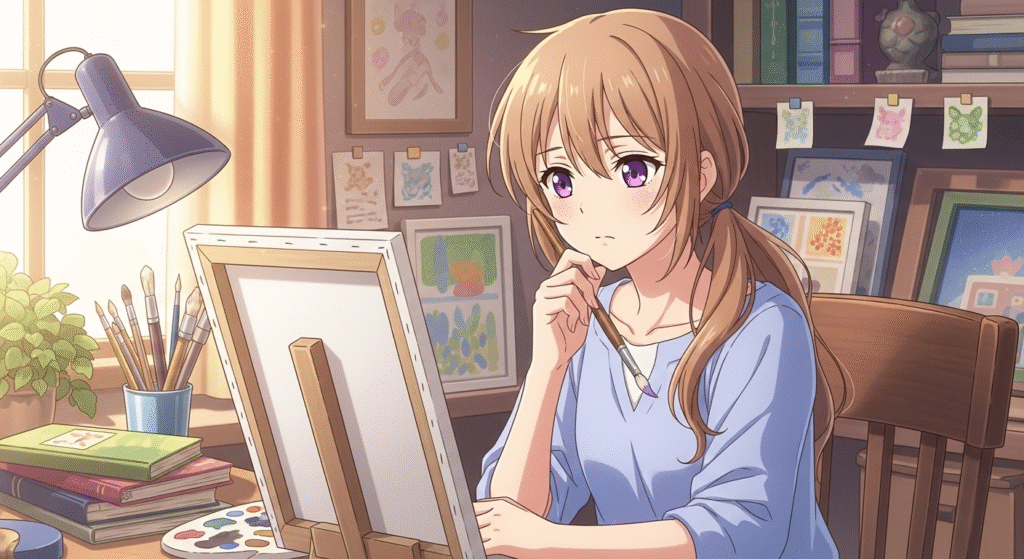目次
ゼロイチでの創造が苦手な自分
これは昔から思っていることなのだが、自分はゼロイチで何かを生み出すことについてはあまり得意ではないというか、むしろ苦手だなと思っている。
何も無いところから何かを作るということは、一種の才能のようなものが関係していると思う。自分はものづくりは好きだが、基本的に最初の一歩のモチベーションは人に頼まれるとか、必要に迫られてというのが多い。
例えば、真っ白なキャンバスを前にした時の感覚というのは、まさにこの苦手意識を表している。絵を描くにしても、文章を書くにしても、プログラムを書くにしても、最初の一筆目、一文字目、一行目を何にするかで躊躇してしまう。これは単純に「やる気がない」とか「能力がない」という話ではなく、むしろ「選択肢が無限大にある状況での決断」に対する苦手意識だと分析している。
面白いことに、一度何かしらの制約や方向性が決まってしまえば、その中で創意工夫をすることについては割と得意だったりする。つまり、完全なる自由よりも、ある程度の枠組みの中での創造性の方が自分には合っているということなのかもしれない。
学生時代のプログラミング学習での経験
かなり昔のことになるが、学生時代にプログラミングを勉強しだした頃、自分の作りたいものというのが思い浮かばなくて困ったことがある。プログラミング自体の学習は一通り終わって、コードは書ける様になったけど、そもそも特に作りたいものが無く、次の一歩を踏み出すまでにかなりの時間がかかった事があった。
課題解決を通じた「ものづくりの楽しさ」の発見
でもその後、人の要望やある特定の課題を解決するような機会に恵まれて、プログラミングやものづくりで問題解決をするということの楽しさを知り、ゼロから一を作る以外でもものづくりの楽しさというのは体験できるんだなということを実感したことを覚えている。
生成AI時代における創作のハードル
今の時代、生成AIが一般的になってきて、最初のアイデア出しのハードルは結構下がってきている気がする。もちろん生成AIで完全に独創的なアイデアが出てくるということではないが、少なくとも自分が考えるよりかはマシなアイデアが出てくるという感覚はある。ただ、そのアイデアを実現するための仕組みについては、生成AIが提案するものは少々大げさではないかと思っている。この点は、まだ人間のほうがマシな案を提案できる気がする。
子供の頃のコンピュータと現在の生成AI
子供の頃の自分にとって、コンピュータというのは自分の苦手な領域を代替したり、得意な領域を伸ばす夢のマシンのように見えたものだが、今の時代は生成AIがこれに当てはまるのかもしれない。自分が子供の頃、PCの性能向上はまさに日進月歩であり、去年出たパソコンと今年出たパソコンでは天と地との差があるくらいに性能向上が著しかった。
急速に進化する生成AIの世界
生成AIもまさに今こんな状況であって、先月出たモデルの性能を今月出たモデルが大幅に上回るみたいなことが立て続けに起こっている。黎明期ならではの、AIを使いすぎると馬鹿になるとかならないとかの論争が繰り広げられており、純粋にこの界隈を追っていくのは楽しい。
自分の性格とアウトプットについて
自分はものづくりや文章作成は結構好きな方だが、どうしてもゼロイチをやるのが億劫で腰が重くなってしまう。ブログもたまにしか書かないのもまあそれが理由だろう。
今後の展望
生成AIとかその他ツールをいい感じに活用して、自分のアウトプットのクオリティを上げていきたいものである。
他の人との比較で見えてくる違い
社会人になってから様々な人と仕事をする中で、「ゼロイチが得意な人」と「自分のような人」の違いがより明確になってきた。ゼロイチが得意な人の特徴を観察してみると、いくつかの共通点があることに気づく。
まず、彼らは「とりあえずやってみる」ことに対する抵抗感が非常に少ない。完璧でなくても、まずは形にしてみる。そこから改善していけばいいという考え方ができる。一方、自分は最初から完成度の高いものを作ろうとしてしまい、結果として手が止まってしまうことが多い。
また、彼らは失敗を恐れていないように見える。正確には、失敗を「学習の機会」として捉えている。自分の場合、失敗することで時間や労力を無駄にしてしまうのではないかという不安が先立ってしまう。
制約があることで発揮される創造性
面白いことに、自分の場合は制約がある方が創造性を発揮できることがある。例えば、既存のコードベースに新機能を追加する場合、現在のアーキテクチャの制約の中で最適解を見つけることについては比較的得意だ。
ブログ記事を書くときも、特定のテーマが決まっている場合(例:技術的な解説記事、体験レポートなど)の方が筆が進みやすい。テーマが決まっていることで、「何を書こうか」ではなく「どう書こうか」に集中できるからだろう。
これは「制約は創造性を高める」という一般的な法則と合致している。無限の可能性があると選択肢が多すぎて迷ってしまうが、適度な制約があることで思考の方向性が定まり、その範囲内での最適化に集中できるのだ。
生成AIを活用した創作プロセス
最近では、生成AIを「創作の相棒」として活用することで、従来の苦手意識を克服できるケースが増えてきた。具体的には以下のような使い方をしている:
- アイデアの種まき:漠然としたテーマをAIに投げかけて、複数のアプローチやアイデアを提案してもらう
- 構成の叩き台作成:記事や資料の大まかな構成をAIに考えてもらい、それを自分なりに調整する
- 表現の多様化:同じ内容を異なる表現で書いてもらい、その中から自分の感覚に合うものを選ぶ
これらの手法により、「白紙から始める」ストレスを大幅に軽減できている。AIが作ったものをそのまま使うのではなく、あくまで「叩き台」として使うことで、自分らしさを保ちながら創作プロセスを効率化できる。
同じ悩みを持つ人へのアドバイス
もし同じような悩みを持つ人がいるとすれば、以下のようなアドバイスをしたい:
1. 完璧主義からの脱却
最初から完璧なものを作ろうとしない。「まずは動くもの」「まずは形になるもの」を目指す。改善は後からいくらでもできる。
2. 制約を積極的に設ける
自由度が高すぎると迷ってしまうので、意図的に制約を設ける。例えば、「1時間で書く」「500文字以内で書く」「特定の技術のみを使う」など。
3. 他人の要求や課題を起点にする
自分のオリジナルアイデアに固執せず、他人の要求や既存の課題を解決することから始める。これにより、「何を作るか」よりも「どう作るか」に集中できる。
4. テンプレートやフレームワークを活用する
既存のテンプレートやフレームワークを使うことで、構造的な部分は省略し、本質的な内容に集中できる。
5. 小さく始める
大きなプロジェクトを最初から目指すのではなく、小さな成功体験を積み重ねる。小さな達成感が次への動機となる。
組織や チームでの活かし方
個人の特性を理解することで、チームでの役割分担も効率的になる。自分のような「ゼロイチが苦手」なタイプは、以下のような場面で力を発揮できる:
- 既存システムの改善・最適化
- 要件定義やドキュメント作成
- コードレビューや品質管理
- プロジェクトの後半フェーズでの仕上げ作業
一方、アイデア創出や初期の方向性決めは、ゼロイチが得意な人に任せるという分業体制を作ることで、チーム全体の生産性を向上させることができる。
重要なのは、自分の特性を欠点と捉えるのではなく、「個性」として受け入れ、それを活かせる場所や方法を見つけることだ。
まとめ:自分らしい創作スタイルの確立
結局のところ、創作には様々なスタイルがあり、ゼロイチで生み出すことだけが価値のある創作ではない。既存のものを改良したり、異なる要素を組み合わせたり、課題解決型のアプローチを取ったりすることも、立派な創作活動だ。
現在の生成AI時代は、従来「創作の入り口」として高いハードルだった「最初のアイデア出し」を大幅に低減してくれている。これにより、自分のような人間でも、より気軽に創作活動に取り組めるようになった。
大切なのは、自分の特性を理解し、それに合った方法とツールを見つけることだ。そして、完璧でなくても、まずは形にしてみる勇気を持つこと。継続的な改善により、最終的には満足のいく成果物を作り上げることができるはずだ。
生成AIやその他の技術の進歩により、創作の方法論は今後も変化していくだろう。その変化を楽しみながら、自分なりの創作スタイルを確立していきたい。